近年「生成AI」という言葉をよく耳にします。さまざまなコンテンツを自動で作り出す生成AIは、Webライターの仕事に大きな影響を与える可能性も秘めています。
もはやWebライターにとって、生成AIの活用スキルは「必須」といっても過言ではありません。しかし「生成AIって何?」「なんとなく難しそう…」といった疑問や不安を感じている人もいるはずです。
そこで今回は、Webライターが理解したい「生成AIの基本知識」を解説します。生成AIを使いこなす前に「どのように活用すべきか」「なぜ活用すべきなのか」といった基礎知識がテーマです。
生成AIが「Webライターの仕事を奪うのではないか」と不安を感じている人も、ぜひ当記事を読んでみてください。生成AIは使い方次第でWebライターの強力な武器となり、仕事の効率化や品質向上に大きく貢献するはずです。
運営者プロフィール

- 2020年:未経験からフリーランスのライターに
- 2023年:ライター月収37万円を達成
- 2024年:電子書籍を出版
「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。
運営者プロフィール

- 2020年:未経験でフリーランスのライターに
- 2023年:ライター月収37万円を達成
- 2024年:電子書籍を出版
「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。
生成AIとは?
人工知能の一種である生成AIは、学習データをもとに新しいコンテンツを生み出す技術です。文章や画像などのデータに含まれるパターンや関係性を把握し、人間が指示したテーマやキーワードに沿って、新しいコンテンツを作り出します。
たとえば「Webライター」に関する情報を生成AIに与えます。
すると、生成AIは「Webライター」というキーワードに関連する情報(SEO・文字単価など)を学習します。そして「Webライターに役立つ記事を書いて」と指示すると、学習した情報をもとに「SEOの知識」や「案件の受注方法」などを解説する文章が生成されます。
人間は過去の経験や知識をもとに、新しいアイデアを考えたり文章を書いたりします。そして、生成AIは人間から学習した経験や知識の「データ」をもとに、コンテンツ生成の流れをコンピューターで再現しています。
 taku
taku生成AIが新しいコンテンツを生み出す仕組みは、人間が考え、行動する流れとほとんど同じです。
生成AIの種類とWebライターの活用例
生成AIには、さまざまな種類があります。
生成AIを活用するなら、単独ではなく組み合わせて使うのが効果的です。たとえば、文章生成AIで原稿を生成し、画像生成AIでアイキャッチや図解を作成すれば、1記事分のデータが完成します。さらに、原稿データを音声生成AIで音源化すれば、音声配信用のファイルに変換が可能です。
Webライターによる生成AIの活用は、仕事の仕方やキャリアに大きな影響を与える可能性が秘められています。それぞれの特徴を理解しながら、効果的に生成AIを活用してみましょう。
文章生成AI
文章生成AIは、文章の執筆や読み込みに特化したツールです。Webライターであれば、文章生成AIを以下の業務に活用できます。
- 執筆
- 要約
- 翻訳
- 校正
- 記事本文の執筆
- 記事本文のリライト
- 記事構成案の作成
- 記事タイトル案の作成
- 誤字脱字のチェック
たとえば「SEOの基礎知識を解説する記事の構成案を考えて」と指示します。すると、生成AIが学習したデータからSEOに関するキーワードや情報を組み合わせ、新しい記事の構成案を提案してくれます。
そして「構成案をもとに記事の本文を作成して」と指示すれば、各見出しごとの文章を生成してくれます。
文章執筆が主となるWebライターにとって使用頻度が高く、効果的に使いこなしたい生成AIです。
画像生成AI


画像生成AIを活用すれば、指示に基づいた画像を生成してくれます。Webライターの使いどころとしては、記事に挿入する図解やアイキャッチ画像の作成です。
- 図解
- アイキャッチ
- アイコン
たとえば「パソコンで作業するネコ」と生成AIに指示すると、その指示にあった画像を生成してくれます。記事のテーマやサイトのコンセプトにあったアイキャッチの作成に便利です。
また、本文の内容に適した図解の作成を指示できる生成AIも存在します。図解のデザインやレイアウトの参考例として、生成AIの作成物を活用するのも効率的です。
音声生成AI
音声生成AIの活用用途は、おもにテキストから音声への変換です。たとえば、記事の読み上げ音声を作成すれば、Podcastやオーディオブックとして配信できます。
また、動画コンテンツの話者(スピーカー)としても活用されています。自分の声で配信することに抵抗がある人は、音声生成AIに代役を務めてもらうのも効果的です。
YouTubeでは「ヒカキンさん」や「ひろゆきさん」の音声を再現するツールが広く利用されています。



あまりにも自然な音声だったので、初めて聞いたときはツールを使用していることに気がつきませんでした。
Webライターが生成AIを使うメリット
ここからは、Webライターが生成AIを使うメリットを以下の4つに絞って解説します。
Webライターが生成AIを効果的に活用すれば、仕事を効率化したり幅を広げたりといったメリットが期待できます。
執筆時間の短縮(効率化)
生成AIを活用すれば、執筆時間を短縮できます。執筆業務が主となるWebライターにとって、執筆時間の短縮は大きなメリットです。
生成AIは本文の執筆だけでなく、構成案の作成や文章のリライトにも活用できます。キーワードやテーマに沿っていくつかのアイデアを提示してくれるので、一から自分で考えるよりも短時間でコンテンツの作成が可能です。
さらに、文章の校正やリライトにも活用できます。誤字脱字や文法ミスを自動的にチェックしてくれるため、自分で何度も読み返す手間が省けます。
キーワードの追加や文章の言い換えなどを指示すれば、リライトの自動化も可能です。
アイデア出しのサポート
文章の表現に悩んだときも生成AIが役立ちます。下書きの一部をもとに「別の表現を提案して」と指示するだけで、複数の言い換え表現を提示するような使い方も可能です。
「どうしようかな?」と悩む時間を短縮できるだけでなく、複数の案を比較検討しながら表現の幅を広げられます。
また、生成AIの活用は、自分では思いつかない視点や意外な組み合わせの発見に効果的です。たとえば「地方移住」に関する記事を書く場合には、生成AIに「メリット・デメリット」や「成功の秘訣・後悔しないコツ」などを質問するかと思います。



いくつかのアイデアを確認した後に「不足している観点があれば教えて」と質問すれば、自分では思いつかなかった観点の気づきにつながります。
Webライターが意識すべき観点は、読者が求める情報を漏れなく提供することです。しかし、ジャンルやテーマによっては、アイデアが枯渇してしまう可能性も多々あります。だからこそ、生成AIは、Webライターのアイデア出しをサポートする有益なツールです。
幅広い表現の提案
幅広い表現の提案も生成AIの得意分野です。



僕自身はキャッチコピーを考えるのが苦手ですが、生成AIを活用すればテーマに沿ったアイデアを提案してくれます。
たとえば「夏の海の魅力」をテーマにキャッチコピーの提案を指示してみます。すると、生成AIは以下のようなキャッチコピーを提案してくれました。
「エメラルドグリーンの海で、最高の夏休みを!」
「波の音に癒される、至福のひととき」
「太陽と砂浜が織りなす、感動の絶景」
提案された表現を参考例として活用すれば、自分自身の文章表現の幅を広げられます。生成AIは複数のアイデアをスピーディに提案してくれるので、比較検討したい場合にも便利です。
SEOの対策(注意点あり)
生成AIは、SEOの対策にも活用できます。たとえば、対策キーワードを含むタイトル案や見出し案の生成、さらには競合サイトのURLから記事構成や対策キーワードの分析も可能です。
一般的なSEOに用いられるルールを生成AIに伝えれば、対策が施された文章を執筆できます。ただし、生成AIが執筆した文章をそのまま使うだけでは、SEOの効果を期待できません。
生成AIは人間が書いた文章(データ)を参考にしているため、オリジナリティに欠ける場合があるからです。
Googleをはじめとする検索エンジンは、オリジナリティの高いコンテンツを評価する傾向にあります。生成AIを活用してSEOを対策する場合は、以下のように必要に応じてライター自身が修正・加筆をする対策も重要です。
- 独自情報を追加する:自分自身の経験や取材で得た情報などを追加する
- 具体例を追加する:具体例を示して文章の説得力を高める
- 文章表現を工夫する:読者に寄りそった言葉やわかりやすい比喩表現に言い換える
- 読者の疑問に答える:読者の疑問を先回りして解決する(Q&A形式など)
生成AIの活用は、あくまでも「60~70点」のベースを作成するための効率化です。SEOの効果を高めるためには、ライター自身の工夫や編集で100点に近づける必要があります。
生成AIのデメリットと注意点
Webライターにとって便利な生成AIですが、デメリットや注意点も存在します。生成AIを安全かつ効果的に活用するためには、以下のようなポイントの理解が重要です。
情報の正確性を担保できない
生成AIが出力する情報は、必ずしも正確であるとは限りません。学習したデータに基づいて文章を生成するため、誤った情報や古い情報を含んでいる可能性があります。
また、事実と異なる情報を、あたかも事実であるかのように提示する「ハルシネーション」が発生することも。生成AIが出力した文章をそのまま使用せず、必ず自分で情報の正確性を確認する「ファクトチェック」が必要です。
ファクトチェックでは、以下のような信頼できる情報源を参照します。
- 官公庁のWebサイト
- 専門家の論文
- 信頼できるメディアの報道
とくに人名・地名・数値データ・歴史的な出来事など、正確性が求められる情報については念入りにリサーチしましょう。
オリジナリティが出せない
大量のデータを学習している生成AIは、文章表現が無個性になりがちです。そのため、生成AIが出力した文章をそのまま使うと、オリジナリティがなく、どこかで見たような印象を与えてしまう可能性があります。
SEOに携わるWebライターとしては、独自性のある記事制作が求められます。だからこそ、生成AIが出力した文章をベースに、自分自身の言葉で表現を修正したり、具体例や体験談を追加したりする対策が必要です。
- 自分の意見や感想を追加する
「私は生成AIを〇〇のように活用しています」
「生成AIを使って〇〇という課題を解決できました」 - 具体的なエピソードを追加する
「以前、生成AIを使って記事を作成したら、〇〇という失敗をしました。その経験から、〇〇すべきだと学びました」 - 読者への語りかけを追加する
「生成AIの活用するとき〇〇に困っていませんか?」
「生成AIを使って見たら〇〇に疑問が残りませんか?」
上記のような要素を追加すると、記事にオリジナリティや個性を加えられます。筆者の体験談や学びは「生成AIが学習できないデータ」です。
ささいな変化ではありますが、記事のオリジナリティを加えるために役立ててみましょう。
AIっぽい文章になりがち
生成AIは、文法的に正しい文章を生成できます。しかし、文章のリズムや感情表現を考慮して使い分けられません。
そのため、生成AIが出力した文章をそのまま使うと、単調な印象を与えてしまう可能性があります。生成AIが普及するほどに、文章に感じる「AIっぽさ」が顕著になっていくはずです。
生成AIが出力した文章を、より魅力的で読みやすくするためには、以下の点に注意して編集しましょう。
- 声に出して読む
文章を声に出して読むと、リズムやテンポの悪さに気づきやすくなります - 接続詞を適度に使い分ける
「しかし」「そのため」などの接続詞を適度に使い分けると、文章の単調な流れを改善できます - 文末表現に変化をつける
「です」「ます」の文末表現だけでなく、体言止めなどの変化をつけると文章にリズムが生まれます - 比喩表現を使う
適度に比喩表現を使うと、文章表現の幅が広がります - 段落分けを適切に行う
適切な長さで段落を分けると、文章の視覚的な読みやすさが増します
生成AIの選び方(4STEP)
さまざまな企業から展開されている生成AIは、それぞれ機能や料金体系が異なります。目的や用途に適したツールを見つけるために、生成AIの選び方を「4つのステップ」に分けて解説します。
STEP1:目的・用途を明確にする
生成AIを選ぶうえで重要なポイントは、ツールを導入する目的と用途を明確にすることです。目的と用途を決めておかないと、どの生成AIが自分に適しているのか判断できません。
まずは、以下のような観点で、生成AIを「なんのために使いたいのか」と考えてみましょう。
- 記事制作を効率化したい
- SEOの改善に活用したい
- マーケティングに役立てたい
記事の構成案や本文の下書きを生成AIに任せると、記事制作の時間を短縮できます。図解の作成が苦手であれば、生成AIでデザインやレイアウトのサンプルを作成するのも便利です。
とくに生成AIは、苦手分野の克服に役立ちます。生成AIの力を借りれば、SEOの知識が乏しくてもキーワード選定や競合サイト分析などにチャレンジできます。
読者の注目を集めるような記事タイトルやキャッチコピーの提案も生成AIの効果的な活用方法です。
また、文章執筆に絞るとしたら「どのような文章を書きたいか」と考えてみるのも大切です。
- Web記事(SEO記事)
- コラム
- インタビュー記事
- SNS投稿文
- メルマガ
Web記事やコラムなど、掲載するメディアや媒体によって執筆する文章のテイストは異なります。ライティングに特化した生成AIを活用するのであれば、文章のテイストに適したツールを選ぶべきです。



もしくは、生成AIに対して、文章のテイストが伝わるような指示(プロンプト)を意識する必要があります。
STEP2:必要な機能を確認する
目的と用途が明確になったら、生成AIに求める機能をチェックしましょう。生成AIによって、少なからず「得意・不得意」の差があります。自分の目的を達成するためには、必要とする機能に適した生成AIを選ぶのがおすすめです。
といっても、あまり難しく考える必要はありません。Webライターの業務で生成AIを活用するなら、まずは以下の3種類だけ把握しておけば十分です。
- ChatGPT
- Gemini
- Claude
いずれの生成AIも「執筆して」「構成を考えて」「添削して」のように指示をすれば、要求に応えてアウトプットしてくれます。ただし、それぞれの生成AIには出力結果の細かな違いがあるため、まずは無料アカウントで使い比べてみるのがおすすめです。
STEP3:料金体系を比較する
以下のように、生成AIの料金体系にはさまざまなプランがあります。
- 無料プラン
- 有料プラン(月額・年額)
- 有料プラン(従量課金制)
まずは使い勝手を確認するため、無料プランを利用すれば問題ありません。ただし、生成コンテンツの質を高めるためには、必要に応じて有料プランの活用も検討すべきです。
無料プランと有料プランの違い
一般的な生成AIの契約プランは、無料と有料に分かれています。おもな違いは、以下のとおりです。
| おもな違い | 無料プラン | 有料プラン |
|---|---|---|
| メリット | 費用がかからない 気軽に試せる | 機能が充実している生成できる 文章量が多いサポートが充実している |
| デメリット | 機能が制限されている生成できる 文章量に制限がある | 費用がかかる |
| こんな人におすすめ | 初めて使う人 お試しで使ってみたい人 | 本格的に業務で活用したい人 コンテンツの作成頻度が高い人 |
無料プランは気軽に試せる反面、機能や文字数に制限があります。また、生成AIが参照できるデータ量に限りがあるため、生成されるコンテンツのクオリティに「もの足りなさ」を感じる可能性も。
有料プランであれば、ほぼすべての機能を利用できます。ただし、契約内容や使用状況に応じて費用が発生するため、活用する頻度や目的にあわせてプランを検討しましょう。
有料プランの料金体系
有料プランの料金体系は、おもに以下の3種類に分かれます。
| 料金体系 | 特徴 |
|---|---|
| 月額料金制 | 毎月一定の料金を支払うことでツールを利用できる |
| 年額料金制 | 年単位で料金を支払うことでツールを利用できる (年間契約することで月額料金が割引になる場合も) |
| 従量課金制 | ツールの利用状況に応じて料金を支払う (ポイントを購入してツールを利用するパターンも) |
利用状況に応じて支払う従量課金制であれば、費用の節約が期待できます。ただし、生成AIの使用頻度が高い場合は、かえって費用の負担が増してしまう可能性も。
ChatGPTやGeminiといった主要な生成AIは、ほとんどが月額料金制を採用しています。業務用途で毎月の使用頻度が高い場合は、年間契約で割引を適用するのもおすすめです。
STEP4:使いやすさをチェックする
生成AIを初めて使うときには、操作方法に難しさを感じてしまいます。そこで、以下の観点で使いやすさをチェックしましょう。
- 利用ユーザー数が多いかどうか
- 日本語対応しているかどうか
- 問い合わせサポートがあるかどうか
使いやすい生成AIを選ぶ重要ポイントは、利用ユーザー数の多さです。利用ユーザー数が多いほど、基本的な使い方や困ったときの対処法を「ネットで解説している人がいる」と期待できます。
生成AIを初めて使うときは「誰かの解説」を参考にするのが基本です。利用者が多い生成AIであれば、Web記事やYouTubeの動画で解説コンテンツを見つけられます。
生成できるコンテンツの自由度が高く、指示の出し方次第でクオリティも変わるため、参考にできる「お手本」がないと苦戦してしまいます。
とくに海外製の生成AIは英語表記がベースとなるため、各種機能や使い方を独学で把握するのは困難です。生成AIの仕組みを理解し、使い方を分析するのは「プロ」に任せて、お手本を活用しながら効率的に使いこなしましょう。



もし、日本語に対応していたり問い合わせサポートが利用できたりしたら「ラッキー」だと思って有効活用するのが得策です。
代表的な3つの生成AI
ここで、代表的な生成AIを3つ紹介します。個人的に使用してみた感想としては、Webライターの業務で使用するなら以下のいずれかを活用すれば十分です。
| 生成AI | 特徴 |
|---|---|
| ChatGPT | OpenAIが開発した高性能なAIチャットボット。 文章生成、要約、翻訳、プログラミングコード生成など、幅広いタスクに対応。 会話形式で指示を出せるため、初心者でも使いやすいのが特徴。 |
| Gemini | Googleが開発した生成AI。 Google検索との連携に対応しており、最新情報に基づいた文章生成が可能。 画像生成機能も搭載。 |
| Claude | Anthropicが開発した生成AI。 長文でもより自然な日本語で生成可能。 ハルシネーション(AIの誤回答)の少なさや回答の安全性に優れている。 |
いずれの生成AIも性能に優れており、すべての有料プランに加入する必要はありません。それぞれに異なる特徴がありますが、まずは1~2つに絞って深く使いこなしていくのがおすすめです。



僕自身は、ChatGPTとGeminiの有料プランを利用しています。
また、上記以外にも日本語に特化した文章作成AIツール「Catchy」やSEOに強いAIライティングツール「Transcope」など、文章執筆に特化した生成AIもあります。特化型の生成AIは用途が限定されるため、必要に応じて使用するかどうかを検討しましょう。
生成AIの料金プランと機能比較
| 生成AI | 料金プラン | おもな機能 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | 無料プラン Plusプラン:月額20ドル Proプラン:月額200ドル | 文章生成、質問応答、要約、翻訳、プログラミングコード生成など | 幅広いタスクに対応 会話形式で指示が可能 |
| Gemini | 無料プラン Google One AI プレミアムプラン:月額2,900円 ※Google AI Studioにて無料利用が可能 | 文章生成、質問応答、要約、翻訳、画像生成、Google検索との連携など | Google検索に基づいた文章生成 画像生成も可能 |
| Claude | 無料プラン Proプラン:月額20ドル | 文章生成、質問応答、要約、翻訳、長文コンテンツ作成など | 長文生成が得意 AIの倫理的な問題に配慮 |
生成AIの料金プランや機能は、変更される可能性があります。最新情報は公式サイトで確認してください。
生成AIを使うときの注意点
生成AIは便利なツールですが、万能ではありません。誤った使い方でライター自身の評価を下げないためにも、以下の観点に注意しましょう。
必ず人の手で編集する
生成コンテンツの質を高めるなら、誤りや改善点のチェックが欠かせません。AIが生成した文章は、文法的に正しくても、不自然な表現や言い回しが含まれることも多々あります。
人間の言葉のニュアンスや文脈をAIが完全に理解できないからです。
「彼はとても背が高い」という文章を「彼は非常に身長が高い」と生成してしまう可能性がある。
また、生成AIは、読者の感情や興味を考慮した文章生成が苦手です。読者にとって魅力的で読みやすい文章を書くためには、やはり人間の判断を加えた修正が求められます。具体的には、以下のような観点で編集(修正)しましょう。
- 不自然な表現や言い回しをより自然な表現に修正する
- 文と文の不自然なつながりを修正する
(接続詞を追加する・文の順序を入れ替える) - 読者にとって不足している情報があれば追加する
- 不要な情報や重複している情報があれば削除する
- 抽象的な表現を具体例を用いてわかりやすく説明する
ファクトチェックをする
AIが生成した文章には、誤った情報や古い情報が含まれている可能性もあります。AIが参照する学習データが必ずしも正しいとは限らないため、信頼できる情報源(官公庁サイトやメーカー公式サイトなど)でファクトチェック(事実確認)が必要です。
とくに専門的な分野や最新の情報については、知識の価値が高まりやすく、より正確なファクトチェックが求められます。
固有名詞・数字・日付など、情報に間違いがないかどうかを念入りに確認しましょう。
また、世の中には、頻繁に新しい言葉(固有名詞や造語など)が生まれています。広く浸透していない新しい言葉や一部の範囲で用いられる言葉など、生成AIが把握しきれない情報も少なくありません。
著作権・商用利用の可否を確認する
生成したコンテンツが既存コンテンツと酷似していると、著作権侵害となる可能性があります。学習データを参考に生成されるコンテンツは、意図せず既存コンテンツと似てしまう可能性も少なくありません。
たとえば、AIが生成した文章を公開する場合は、既存コンテンツに類似文章がないかどうかをチェックしましょう。



「CopyContentDetector」のようなチェックツールを活用すると便利です。
また、生成AIによっては、商用利用(商業目的での利用)が制限されている場合もあります。生成AIごとの利用規約をよく確認しながら、生成コンテンツの利用可否もチェックしておきましょう。
生成AI時代のWebライターはどうなる?
生成AIの登場は、Webライターの仕事に良くも悪くも大きな変化をもたらしています。
「生成AIはWebライターの仕事を奪うのか?」
「生成AI時代にWebライターとして生き残るためにはどうすれば良いのか?」
Webライターは、生成AIとどのように向き合えばよいのでしょうか?
そこで、生成AI時代を生き抜くため、Webライターの将来展望について考察してみました。
生成AIの登場に不安を感じている人もいるかもしれません。しかし、生成AIの登場は、Webライターにとって「脅威」ではなく「チャンス」です。Webライターとしてさらに活躍するためのヒントを見つけましょう。
生成AIがライター業界にもたらす変化
生成AIの登場により、Webライターの仕事は「無くなるのではないか」という声も聞かれます。しかし、結論から言えば、生成AIはWebライターの仕事を完全に奪うものではありません。



生成AIはWebライターの仕事をサポートする「ツール」であり、使い方次第で「敵」にも「味方」にもなります。
生成AIは、Webライターの仕事に以下のような変化をもたらすと予想できます。
- 単純作業の自動化
- コンテンツの大量生産
- SEOの変化
- 新たな仕事(役割)が生まれる
単純作業の自動化
記事構成案の作成や誤字脱字のチェックなど、Webライターが担当していた単純作業の一部が生成AIで自動化できます。Webライターは、よりクリエイティブな仕事や「人間でなければできない仕事」に集中できます。
コンテンツの大量生産
生成AIを活用すると、短時間で大量のコンテンツを作成できます。より効率的にWebサイトのコンテンツを充実させたり、複数のメディアで情報発信したりできます。
SEOの変化
生成AIは、SEOに強い文章の作成や役立つ情報のリサーチに役立ちます。ただし、Googleをはじめとする検索エンジンは、生成AIが出力したコンテンツを高く評価しない可能性も。今後の対策としては、よりオリジナリティがあり、個人の体験やエピソードを重要視したコンテンツが求められます。
新たな仕事(役割)が生まれる
生成AIの登場により、新たな仕事が生まれる可能性もあります。たとえば、AIが生成したコンテンツの「チェック」や「編集」、さらには生成AI自体を使いこなすライターやディレクターなど。生成AIを正しく活用するスキルがある人材の需要も高まるはずです。
Webライターに求められるスキル
生成AI時代にWebライターとして活躍するためには、大きく分けて2種類のスキルが求められます。
- 生成AIを使いこなすスキル
- 生成AIの弱点を補うスキル
生成AIを使いこなすスキル
生成AIを使いこなすには、まずは使い方を理解する必要があります。どのような指示を出せば「質の高い文章が出力されるか」といった観点で、生成AIを工夫しながら活用するスキルです。
また、生成AIが出力した文章を正しく編集するスキルも求められます。文章から生じた不利益に対して、生成AIは責任を取ってくれません。だからこそ、Webライター自身で修正や訂正を判断できる編集スキルが必要です。
生成AIから質の高いアウトプットを引き出すためには、効果的な指示(プロンプト)を作成するスキルが欠かせません。プロンプトの作成スキルを高めるためには、生成AIの特性を理解する必要があります。
「どのような指示を与えれば、どのような結果が得られるのか」といった観点で、まずは生成AIを試しに使ってみるのがおすすめです。
他者が作成したプロンプトも参考にしながら、実践的なプロンプトの作成スキルを磨いてみましょう。
生成AIが出力した文章は、必ずしも完璧であるとは限りません。論理的な矛盾や情報の不足が発生する可能性も多々あります。Webライターには、生成AIが出力した文章を「正しく・読みやすく編集する能力」が求められます。
編集力を高めるためには、文章の構成や文法など、執筆にかかわる幅広い知識を身につける必要があります。AIに頼らなくても記事を制作できるスキルが必要であり、文章の良し悪しを判断できる執筆経験も欠かせません。



他者の記事を編集したり、自分の記事を編集してもらったりするなど、実践的な編集スキルを磨いておきましょう。
生成AIの文章には、誤った情報や古い情報が出力される可能性も少なくありません。そのため、生成AIが出力した情報の正確性を確認する対応(ファクトチェック)が求められます。
ファクトチェック能力を高めるためには、信頼できる情報源(官公庁のWebサイトや専門家の論文など)を参照する習慣化が大切です。また、情報源の信頼性や鮮度を判断する能力も求められます。
生成AIの弱点を補うスキル
生成AIには「人間らしさ」を表現できない弱点もあります。とくに学習データをもとに文章を生成するAIは、属人的な経験や感情を表現できません。
そして、生成AIの弱点は、活用するWebライターにとっての課題でもあります。生成AIを活用するWebライター自身の評価を下げないためにも、以下のような弱点を補うスキルが必要です。
学習データをもとに文章を出力する生成AIは、オリジナリティのあるアイデアや文章表現の工夫が得意ではありません。Webライターには、生成AIにはない独自の視点や発想で読者の心に響く文章を執筆する表現力が求められます。
表現力を高めるためには、日頃からさまざまな情報にふれ、自分自身の興味関心を広げる意識が大切です。また、さまざまな記事を読んだり、読者と交流したりすることで、新たな発想を得る機会を生み出せます。
特定分野の専門知識をもつWebライターは、生成AI時代においても価値を発揮できます。とくに高度な業務知識が求められる分野(医療、法律、金融、ITなど)は、信頼性を担保するためにも生成AIの出力だけでは代替できません。
専門知識を深めるためには、日頃から経験や学びを蓄えておく意識が必要です。日々の出来事や所感を記録しておき、ときにはSNSで発信もしてみましょう。



今後も需要が高まるであろう実体験を「忘れないための取り組み」が欠かせません。
また、他者の体験談やノウハウにも価値があります。書籍や論文を読んだり、セミナーに参加したりするなど、継続的な学習も心がけましょう。
クライアント対応で気をつけること
生成AIを活用して記事を作成する場合は、クライアントへの対応に注意が必要です。とくに以下の観点については、事前の説明や確認を心がけましょう。
生成AIの使用を事前に伝える
クライアントに無断で生成AIを使用するのは避けましょう。事前に了承を得るためにも「より多くの記事を納品できる」「付加価値の提供に注力できる」のように、生成AIを使用すべきメリットを提案し、クライアントの理解を得るように努めましょう。
生成AIの活用範囲を明示する
クライアントに誤解を与えないように、生成AIの活用範囲を明示するのも大切です。たとえば「官公庁サイトの要約(リサーチ)に活用しました」「執筆後の校正に活用しました」など、生成AIの担当箇所を明確にすると依頼者としても安心できます。
最終的な責任は自分が負う
生成AIは、あくまでも便利なツールです。記事の品質に対する最終的な責任は、Webライター自身が負う意識を忘れないでください。出力結果に誤りがあっても、生成AIは責任を取ってくれません。
出力結果を鵜呑みにせず、ファクトチェックや修正・加筆を欠かさずに実施しましょう。また、クライアントから修正依頼があった場合は、速やかな対応が必要です。
まとめ|生成AIの普及はWebライターのチャンス
今回は「生成AIの基本知識」をテーマに、以下のコンテンツを解説しました。
生成AIのテクノロジーは、想像以上のスピードで日々進化しています。そして、Webライターの仕事にも大きな影響を与え続けています。
僕自身も2022年頃には「生成AIの普及なんて何年も先のこと」「ライターが活用するにしても高額の費用がかかる」なんて話をしていました。しかし、いつの間にか当たり前のように生成AIを活用しており、Webライターの業務に欠かせない存在になりつつあります。
生成AI時代を生き抜くWebライターには、最新のトレンドを常に把握し、今後の可能性を見据える意識が欠かせません。



「AIなんて難しくて使えない」と考えてしまうかもしれませんが、使いこなすライターが増えるほどに、自分の立ち位置を失っていくリスクから目を背けられません。
生成AIの普及は、Webライターにとってチャンスでもあります。生成AIを使いこなし、より高品質なコンテンツを効率的に作成できるようになれば、Webライターとしての価値と活躍の場を広げられます。
僕自身も生成AIに難しさを感じていましたが、使ってみると意外にすんなりと受け入れられました。今後は当メディアでも僕自身の実体験をもとに「生成AIの使い方」を解説していくので、ぜひ一緒に学んでみませんか?
当サイトのコンテンツに対する感想を募集しています。
よろしければ、SNSにて「#ライプロ」とタグをつけて自由な感想を発信してみてください!
発信に気づき次第、リプやリアクションなどさせていただきます。
また、以下のようなご意見・ご要望も募集しています。
- わかりにくい部分があった
- 質問してみたいことがある
- こんなコンテンツがほしい
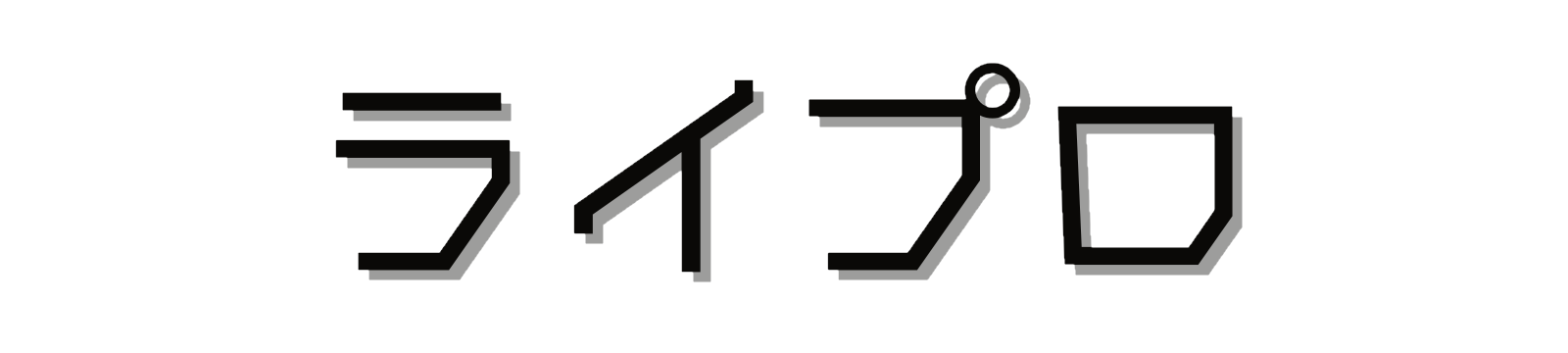
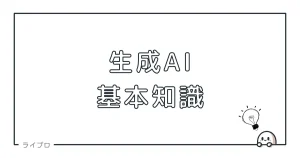
コメント