今回のテーマは「リード文の書き方」です。
Web記事のリード文(導入文)は、読者が本文を「読んでみようかな?」と判断する重要な要素です。
とはいえ、リード文の書き方には、どうしても慣れていないと悩んでしまいます。
そこで、今回解説する5つのステップで、リード文の書き方を実践してみましょう。
運営者プロフィール

- 2020年:未経験からフリーランスのライターに
- 2023年:ライター月収37万円を達成
- 2024年:電子書籍を出版
「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。
運営者プロフィール

- 2020年:未経験でフリーランスのライターに
- 2023年:ライター月収37万円を達成
- 2024年:電子書籍を出版
「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。
リード文が重要な理由
記事の冒頭部分であるリード文は、本文以上に重要と言われています。
読者が最初に読む文章であり、記事全体の印象を左右する重要な要素です。
読者と記事をつなぐ役割がある
リード文が重要視される理由は、読者と記事をつなぐ役割があるからです。
リード文は「導入文」とも呼ばれ、読者を記事本文へと導くための文章を指します。
読者を本文へ導くためには、記事に興味をもってもらうことが重要です。
リード文を読んだ段階で「この記事は役に立ちそうだな」と読者の心を惹きつけましょう。
- 読者の共感を得る
- ベネフィットで期待を高める
- 記事の内容を簡潔に伝える
上記の役割を意識すると、読者と記事の距離を近づけるリード文が書けますよ!
読者に記事を読むメリットが伝わる
読者に「記事を読むメリットがある」と伝えるのも、リード文の重要な役割です。
記事から得られるメリットが悩みの解決に役立つとわかれば、読者は本文まで読み進めたくなります。
- 共感を得る(自分に向けられた記事であると認識してもらう)
- 根拠や理由を示す(記事の内容を信頼してもらう)
上記のように記事を読むメリットが伝われば「自分の悩みを解決できそう!」と読者の期待が高まります。
まさにリード文は、読者に記事の価値を売り込むセールスマンのような役割です。
読者が記事を読むかどうかの判断材料となる
記事の冒頭部分であるリード文は、読者が最初に閲覧するコンテンツです。
リード文が記事の印象を左右するため、読者が本文を読み進めるかどうかの判断材料でもあります。
読者は「知りたい答えがあるか」「読む価値があるか」をできるだけ早く判断したいと考えているはずです。
読み進めるべきかどうかをスムーズに判断できるリード文であれば、読者を満足させられます。
- 記事の概要や得られるメリットを示す
- わかりにくい言い回しや難しい用語を避ける
リード文の書き方
読者が満足できるリード文には、5つの要素が含まれています。
それぞれの要素を意識しながら、リード文を5つのステップで書いてみましょう。
読者の悩みを想定する
まずは読者の悩みを想定して、共感できる言葉を示します。
リード文で共感を得られると、読者自身が記事を自分事と認識して読み進めてくれます。
下記のように、悩みに問いかけたり共感を求めたりしながら読者の心をつかみましょう。
悩みに共感する一言
痩せたいと悩んでいませんか?
さらに深く共感を得るには?
糖質制限にチャレンジしたのに、リバウンドに困っていませんか?
記事で提示する解決方法と読者の悩みがズレていると、読者の気持ちは離れてしまいます。
読者に「あなたのことを理解してますよ」という気持ちを伝えられるように意識してみましょう。
記事から得られるメリットを示す
リード文では、記事を読むと得られるメリットも伝えましょう。
読者にメリットを示すと「じゃあ読んでみようかな」という気持ちになります。
解決方法を提示する
リバウンドしないダイエットには、食事方法の改善が欠かせません。
メリットを提示する
太らない食事方法を理解すれば、無理な食事制限をしなくてもリバウンドしない健康的な食生活が続けられます。
また、読者の心をひきつけるには、記事を読まないと発生するデメリットを示すのも効果的です。
読むべき根拠として「この記事を読まないと損しますよ」と伝えます。
- 食生活で糖質やカロリーを制限しているなら、いますぐにやめてください。
- 不適切な食事制限は、代謝が落ちて痩せにくい身体となってしまう原因です。
人間には「損失回避バイアス」と呼ばれる利得よりも損失のほうが大きく感じる心理的傾向が働きます。
ただし、不安を煽るようなデメリットは、読者にネガティブな印象を与えてしまうので注意が必要です。
デメリットの重要度が高い場合を除き、基本的にはメリットを優先しましょう。
解決できる理由や根拠を示す
読者に記事の内容を信用してもらうため、解決できる理由や根拠を提示しましょう。
読者は「書いてある内容が本当に正しいのかな?」と、基本的に疑いや不安をもっています。
たとえば、下記の記事を選ぶ場合は、どちらを参考にしたいですか?
- 現役携帯ショップ店員がおすすめする「最新スマホ5選」
- 雑記ブロガーがおすすめする「最新スマホ5選」
記事の内容を信用してもらうためには「誰が書いたのか」「どこから得た情報なのか」を裏付ける理由や根拠が必要です。
記事の根拠となる「執筆者の権威性」や「情報源の信頼性」をわかりやすく伝えましょう。
- 専門的な資格や肩書き
(例:ジムトレーナー、FP2級など) - 特定分野での実績
(例:-20㎏のダイエットに成功、副業で月収10万円超え達成など) - 信頼できる情報源
(公的機関、論文、専門家の著書など)
肩書きや実績がなくて悩んでしまう場合は、過去の経験から小さな成果を探してみましょう。
たとえ小さな成果でも、初心者からすれば参考にしやすい身近な目標です。
また、ささいでもリアルな体験談を知りたがる読者は少なくありません。
- ブログ未経験からスタート
- 3ヶ月の継続と収益化を達成
上記の肩書きは、経験者からすれば小さな実績です。
しかし、これから挑戦する初心者には、身近な目標であり、気になる体験談でもあります。
叶えられる未来を示す
記事を読むと叶えられるような、読者の生活がよりよく変化した未来(ベネフィット)を示しましょう。
悩みを解決した未来を想像すると、読者は「実現したい!」の気持ちが高まります。
ベネフィットはマーケティング用語であり、簡潔に説明すると「いい感じになった未来の様子」です。
メリット
太らない食事方法を理解すると、リバウンドしない健康的な食生活が続けられます。
ベネフィット
スリムなスタイルをキープできれば、おしゃれなファッションをさらに楽しめます。
いい感じの未来がイメージできるように、読者の気持ちが盛り上がるようなベネフィットを書いてみましょう。
記事本文の概要を伝える
リード文の締めでは、記事全体のテーマ(概要)を簡潔に伝えましょう。
本文の概要を伝えると、読者が記事のテーマを理解できます。
今回は初心者に向けて、〇〇の書き方について解説します。
失敗を防ぐための〇〇の注意点とコツを紹介します。
また、読者の行動を後押しするようなひと言も効果的です。
「自分でも挑戦できるかも!」と、本文を読み進めるモチベーションが高まります。
すぐに実践しやすい「3つの手順」にまとめました。
〇分で読み終わりますので、ぜひチェックしてみてください。
リード文を書くためのコツ
リード文を書くためには、以下のコツを意識しましょう。
200~400文字でシンプルにまとめる
リード文は、200~400文字でシンプルにまとめましょう。
リード文が長すぎると読者が飽きてしまい、本文を読む前にページから離脱してしまうからです。
検索してきた読者は、悩みや疑問をできるだけ早く解決したがっています。
つまり、だらだらと長文で書いたリード文は逆効果です。
本文にスクロールしてもらうためにも、簡潔でわかりやすいリード文を心がけましょう。
読者の悩みを具体的に想像する
「自分に当てはまる」と感じる悩みを具体的に書けば、リード文は読者の心により深く刺さります。
悪い書き方
仕事を辞めたいと悩んでいませんか?
よい書き方
上司のキツい言動や自分勝手な後輩のフォローなど、職場のストレスに嫌気がさしていませんか?
後者のように情景が浮かぶような書き方は、読者が自分の悩みとして共感しやすくなります。
また、読者の悩みを具体的に想定する方法は、以下の2パターンが一般的です。
- 悩んでいる人の声をリサーチする(アンケートやSNSの口コミなど)
- ペルソナを設定する(人物像を明確にした一人の悩みを想定する)
悩んでいる人の行動や考えを想像すると、読者に深く共感されるリード文が書けますよ。
記事本文のあとに書いても良い
リード文を書くタイミングは、記事本文の執筆後もおすすめです。
リード文は記事全体の要約でもあるため、本文を書き終えてからのほうが内容をスムーズにまとめられます。
記事を書くときは、冒頭のリード文から書き始めてしまいがちです。
しかし、固定概念を捨て、本文から書くことで記事制作が効率よく進むこともあります。
すぐに使えるリード文のテンプレート
ここからは、コピペですぐに使えるリード文のテンプレートを2パターン紹介します。
「製品を紹介する記事」の想定でテンプレートを作成してみました。
悩みや不安の共感を誘うパターン
「○○って本当に効果があるのかな?」
「○○に興味があるけど、自分にもあっているのかな?」
本記事では、上記のような悩みを解決します。
筆者である私自身も、××の悩みを数年間抱えていました。しかし、○○を活用することで改善効果を実感し、いまでも使い方を工夫しながら愛用しています。
そこで今回は、数年間利用してみた経験をもとに、○○を活用するメリットや効果的な使い方を解説します。
- ○○を活用するメリット
- ○○の効果的な使い方
- ○○を使用するときの注意点
上記のテンプレートは、とある製品の購入に迷っている人を想定したリード文です。
テンプレートには、以下のような情報を組み込んでいます。
- 活用すれば悩みを解決できる
- 筆者も実際に活用してる
- 使い方を工夫できる
文章を紹介する製品やサービスにあわせて変更するだけで、幅広く使いやすいリード文です。
記事の概要から伝えるパターン
- ○○が必要な理由
- 5ステップでわかる○○の使い方
- ○○を使用するときの注意点
- ○○のよくある質問
初心者でも手軽に××できると注目を集める○○。しかし、効果を実感できず「本当に必要なの?」と疑問を抱く声もあります。
そこで本記事では、○○の必要性や使い方をわかりやすく解説します。
○○を効果的に活用すれば、専門知識がなくても××に挑戦が可能です。
ただし、適切な使い方を理解する必要があるので、本記事では5つのステップで詳しく解説します。
上記のテンプレートは、とある製品の必要性や使い方を紹介する記事のリード文です。
「使い方」「作り方」のように、方法を解説する記事では悩みへの共感が不要な場合もあります。
そのような場合には、あえて記事の概要(要約)を先頭に配置するのも効果的です。
リード文に必要な「共感」「概要」「ベネフィット」などの要素は、順序を入れ替えても問題ありません。
まとめ|読者に「自分事」と感じてもらおう!
今回は「リード文の書き方」をテーマに、以下のコンテンツを解説しました。
Contents
リード文は、記事の印象を決める重要な要素です。
書き方に悩んでしまうときは、今回解説した「5つの要素」を意識してみてください。
読者に「読んでみようかな!」と感じてもらえるように、魅力的なリード文を書いてみましょう!
当サイトのコンテンツに対する感想を募集しています。
よろしければ、SNSにて「#ライプロ」とタグをつけて自由な感想を発信してみてください!
発信に気づき次第、リプやリアクションなどさせていただきます。
また、以下のようなご意見・ご要望も募集しています。
- わかりにくい部分があった
- 質問してみたいことがある
- こんなコンテンツがほしい
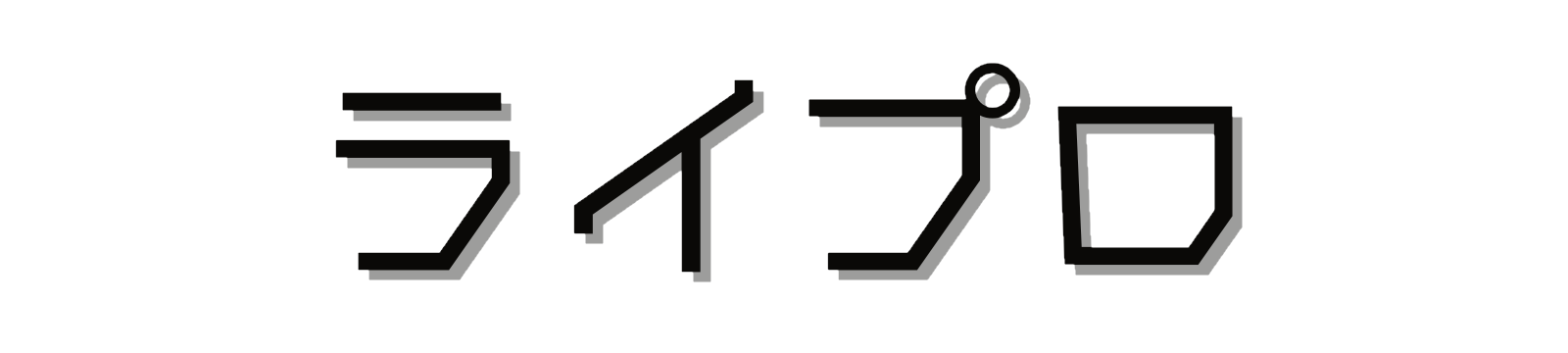
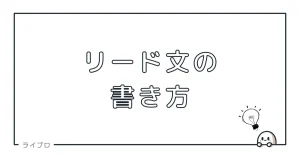
コメント