今回のテーマは「Webライター向けのコミュニティ」です。
Webライターのスキルアップやステップアップに役立つさまざまなコンテンツを利用できます。
また、コミュニティは、ライター同士の交流の場としても有益です。
そこで、僕自身が実際に参加してみて感じた「コミュニティの魅力や注意点」を解説してみます。
運営者プロフィール

- 2020年:未経験からフリーランスのライターに
- 2023年:ライター月収37万円を達成
- 2024年:電子書籍を出版
「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。
運営者プロフィール

- 2020年:未経験でフリーランスのライターに
- 2023年:ライター月収37万円を達成
- 2024年:電子書籍を出版
「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。
コミュニティに参加したきっかけ
「コミュニティに参加してみよう」と思ったきっかけは、ライターとしての伸び悩みを感じていたからです。
頑張って記事を執筆しているけど、評価も単価も上がっていく気がしない。
というより、独学に限界を感じ、評価や単価の上げ方が「わからなくなってしまった」のが本音かもしれません。
停滞感を打破するヒントを見つけるため、ライター歴5年目にしてようやく「他人から教わろう」と決心しました。
「Webライターラボ」を選んだ
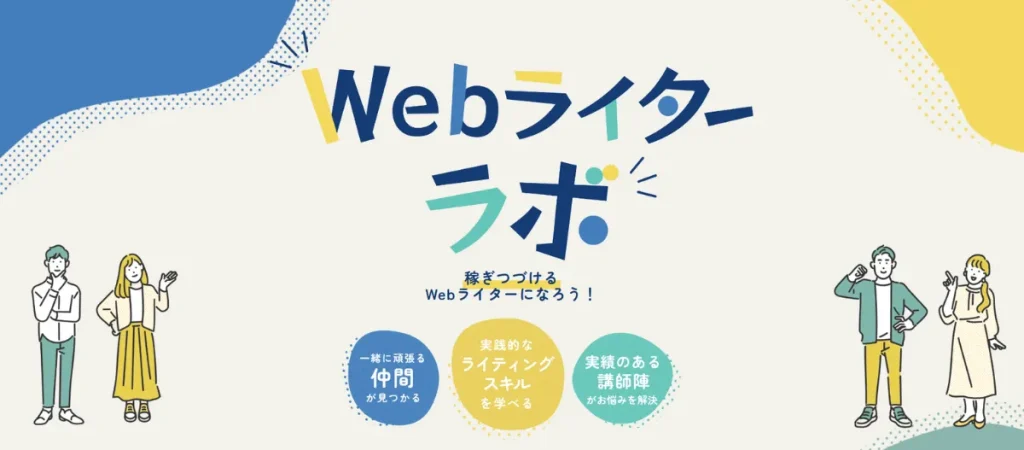
ライター歴5年目のタイミングに、僕は「Webライターラボ」に入会しました。
Webライターラボは、ライティングを学びたい人向けのオンラインサロンです。
数あるコミュニティからWebライターラボを選んだ理由は、運営者の中村昌弘さんや講師の方々から「学んでみたい」と思えたこと。
ライターの第一線で活躍している人たちから学べば、自分に足りない何かを見つけられる気がしました。
 taku
takuちなみに、Webライターラボの存在は、入会する数日前に読んだ下記の電子書籍で知りました。
コミュニティに参加して良かったこと
以下は、僕自身がコミュニティ(Webライターラボ)に参加して「良かった」と思えたことです。
幅広い知識を学べた
Webライターラボに入会したおかげで、さまざまな知識や実践的なノウハウが学べました。
Webライターラボでは初心者向けの基礎知識はもちろん、中~上級者向けのノウハウも学べます。
僕自身は入会時にWebライター歴が5年目に突入していたので、基礎的な学習は求めていませんでした。
そこで、取材のコツや電子書籍の出版方法など、過去に実践したことのないノウハウを優先的に学びました。
- 取材の方法
- 電子書籍の出版方法
- 直営業の方法
- マインド論
- コラムの書き方
上記に挙げたノウハウは、Webライターラボで学んだ「ほんの一部」です。
プレスリリースやホワイトペーパーなど、学ぶまで存在すら知らなかったノウハウも幅広く学んでいます。



SEOしか知らなかった僕にとって、ライター業務の幅を広げるきっかけになりました。
業務の幅が広がった
Webライターラボでノウハウを学んだおかげで、業務の幅を広げられました。
- 電子書籍を出版した
- 取材記事を執筆した
- 直営業で案件を獲得した
独学で学ぼうとすると、どうしても「自分にできそうなこと」「興味があること」を選んでしまいます。
学習テーマが「自分の手が届く範囲」に絞られてしまうため、そもそも挑戦する発想すらなかったかもしれません。
過去の僕自身は、失敗する怖さを感じて「初めての挑戦」を避けていました。
しかし、講義を聞いて仕組みを理解すると、意外に「あれ?できそうな気がする」と思えます。
不安を解消するコツは「知らない」を減らすことなのかも(講師の教え方の上手さにも助けられました)。
また、直営業で案件を獲得できたことも個人的に大きな変化です。
以前までクラウドソーシングサイトに頼っていたため、企業やメディアに直営業をした経験がありませんでした。



直営業の講座に参加し、講師が解説していた方法を実践してみたところ、半年で5件以上の案件を獲得できました。
ライター仲間が増えた
Webライターラボに入会したことで、Webライターの知り合いが増えました。
コミュニティに参加するまでは、業務でかかわる人しか知り合いと呼べるライターがいませんでした。
オンライン講義に参加したり、オフ会に参加りたり。交流の場を広げることで、多くのライターとかかわる機会が増えます。
とくにオフ会に参加した経験は、僕自身の環境が大きく変化した要因です。
リアルで顔を合わせると、やはり関係性がより深まる気がします。



いまでは、定期的にオンライン会をするライター仲間も増えました。
【余談】人と会うことの重要性
ライターになったばかりの頃は「一人でやっていける」と考えていました。
たしかに一人でもなんとかなるのですが、やはり「遠回りしてしまった」という気持ちもあります。
実績のない自分が頭をひねっても、画期的なアイデアは浮かびません。
だからこそ、第三者の意見を取り入れる機会に大きな価値を感じました。
さまざまな人と出会うと、自分は「大したことない」って気づきます。
自分の考えは「完ぺきではない」「間違えるときもある」と認識すべきです。
すると、自分の知識や思いつくアイデアの「範囲の狭さ」を受け入れられます。
コミュニティに参加すると、自分よりもスゴい実績を誇る方々にたくさん出会います。
自分とは異なる意見をスポンジのように吸収していくと、戦略の手札が増えて強くなれた気がします。
難しいと思っていた業務のコツを教えてもらうと、不思議とチャレンジする勇気が湧いてきますよ。
コミュニティには、自分と似たような境遇や立ち位置のライターもたくさんいます。
もちろん、自分よりもライター歴の浅い人もたくさんいます。
自分自身の経験や知識が他者の役に立つ場面も少なくありません。



ちょっとしたアドバイスができたとき、ライターとして活動してきた過去にようやく価値が生まれた気がしました。
行動する勇気が得られた
僕自身はコミュニティに参加したおかげで、行動する勇気が得られました。
- メディアに直営業した
- 取材を依頼した
- オフ会に参加した
コミュニティに参加するライターさんや講師の方々を意識すると、不思議と「行動しよう!」って思えます。
というより、恥ずかしい自分を見せたくなくないから、頑張って行動しているのかもしれません。
メディアに直営業できたのも取材を依頼できたのも、講師に「頑張りました!」って報告したかったからです。



自分自身の殻を破るためには、背中を押してくれる存在やきっかけが必要でした。
コミュニティで気をつけるべきこと
以下は、僕自身がコミュニティ(Webライターラボ)に参加して「気をつけるべき」と思ったことです。
受け身な姿勢で参加しない
コミュニティといえば「他者との交流」のイメージがあります。
しかし、コミュニティに入るだけで仲良く交流できるわけではありません。
他者との交流を求めるのであれば、自分から積極的に行動する必要があります。
オフラインでコミュニケーションをとるのと同様に、仲良くなるには「きっかけ」が必要です。
- コミュニティ上でのやり取り
- SNSでのコミュニケーション
- 対面するイベントに参加
コミュニティ上でのやり取りやSNSでのコミュニケーションを重ねて、徐々に交友関係が広がっていくようなイメージです。
もちろん、コミュニティのメンバーとして、みなさん優しく迎え入れてくれます(Webライターラボはそうでした)。
とはいえ、やはり顔も素性も知らない関係性では、どうしてもお互いに「様子を見てしまう期間」があると思いました。
だから、積極的に自己開示をしながら、自分のことを知ってもらうアクションが必要です。
対面で交流するのが近道
「仲良しのライター仲間を増やしたい!」って人は、対面で交流するイベントに参加するのが近道だと思います。
- オフ会
- オンライン交流会
対面で相手の顔やキャラクターを知ると、やはり関係性がグッと近づく気がします。
僕自身もオフ会で知り合ったライターさんと定期的に交流する機会が増えました。
とはいえ、対面で人と会うのは、けっこうハードルが高い行動です。



僕自身も人と会うのは得意ではありません。本音を言うと、会わなくて済むなら会いたくないほど苦手です。
初めてのオフ会に参加したときなんて、ほとんど記憶がないくらいに緊張しすぎてしんどかったです。
それでも、オフ会をはじめ、人と交流する場に参加して良かったと思っています。
見る専でも問題なし
コミュニティに参加すると「積極的に交流しないといけない」と考えがちです。
実際に積極的に交流したほうが、得られるメリットが大きいのは事実だと思います。
しかし、自分のペースで参加しても問題ありません。
気になる講義だけ見たり、掲示板だけ利用したりと「見る専」で参加している人もいます。
コミュニティに参加する目的は人それぞれです。
勉強やスキルアップを目的に参加するのであれば、無理に他者との交流を深める必要もありません。
僕自身もそうなのですが、他者との交流に苦手意識を感じる人もいます。
有益な講義やコンテンツを活用するだけでもコミュニティに参加する価値はあります。
周囲の盛り上がりがどうしても気になってしまいますが、あまり気にせずマイペースに活用しましょう。
ネガティブな発信をしない
他人との交流に気をつけるためには、ネガティブな発信を避けるべきです。
- 仕事やプライベートの愚痴
- 政治や芸能への不満
- 他者への悪口
本音を言うと、仕事やプライベートの愚痴を吐きたくなるときは多々あります。
しかし、コミュニティは、愚痴を言い合う場ではありません。
個人的には、ポジティブな交流を求めている人が多い印象があります。
愚痴を言い合うのは「仲良くなってから」にしておくのが得策です。
つらいときは相談する
もし、仕事の不満を打ち明けたいときは、愚痴ではなく「相談」しましょう。
悩みや困りごとの相談であれば、サポートやアドバイスを得られる体制が整っています。
- 質問・相談用の掲示板に書き込む
- オンライン面談で話をする
- オフ会で話をする
コミュニティの運営者や講師はもちろん、参加するメンバー同士で情報共有をする機会も少なくありません。
日頃から良好な関係性を築いていれば、周りも親身になってフォローしてくれます。
案件紹介を期待しない
コミュニティに参加すると「案件を紹介してもらえる」と期待しがちです。
しかし、個人的に案件の紹介は、あまり期待すべきではないと感じました。
コミュニティに参加するメンバーが案件を紹介する機能はあります。
しかし、ライターのスカウトではなく、クラウドソーシングサイトと同様に応募形式での案件紹介です。
つまり、案件を獲得しやすいわけではなく、他メンバーとの競争を避けられません。
一般的な案件と同様に提案文の提出が必要ですし、スキルや実績のアピールも欠かせません。
クラウドソーシングサイトと比べれば、ライバルの数は少ないかもしれません。
ただし、コミュニティでスキルアップした中~上級者のライバルも含まれています。
コミュニティで案件を獲得するチャンスはありますが、実績やスキルのアピールが求められることを認識しておきましょう。
Webライター向けコミュニティの選び方
Webライター向けのコミュニティは、調べてみると意外にたくさんあります。
コミュニティによって学べるテーマやジャンル、手法(テキスト・動画)が異なります。
学びたいテーマや携わりたいジャンルが明確に決まっている場合は、コミュニティで「学べるかどうか」をチェックしておくと安心です。



僕が参加しているWebライターラボは、テーマやジャンルが幅広いので「これから見つけていきたい」という人にもおすすめです。
あくまでも個人的にですが、以下の観点でコミュニティを選ぶのがよいかと思います。
- 学びたいノウハウを得られるかどうか
- 教わってみたい講師がいるかどうか
- アクティブなユーザーが多いかどうか
個人的には「アクティブなユーザー」が多いコミュニティを選ぶのがおすすめです。
アクティブなユーザーの多さは、コミュニティの講義やイベント後の「SNSの盛り上がり」で判断できます。
【余談】複数のコミュニティに参加すべきか
| コミュニティ | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 複数に参加する | ・学びの幅が広がる ・交流の幅が広がる | ・費用の負担が大きい ・参加する時間の確保が難しい |
| 一つに絞る | ・深く効率よく学べる ・費用の負担が少ない | ・学びや交流が偏る可能性もある |
| コミュニティ | メリット・デメリット |
|---|---|
| 複数に参加する | メリット ・学びの幅が広がる ・交流の幅が広がる デメリット ・費用の負担が大きい ・参加する時間の確保が難しい |
| 一つに絞る | メリット ・深く効率よく学べる ・費用の負担が少ない デメリット ・学びや交流が偏る可能性もある |
複数のコミュニティに参加すべきかどうかは、正直に言うと「何とも言えない」が結論です。
実際に「幅広い知識を学びたい」「たくさんの人と交流したい」と、複数のコミュニティに参加する人もいます。
ライターの業務は想像以上に幅が広いので、コミュニティによって学べるノウハウに違いがあるのも事実です。
また、参加者の顔ぶれも異なるので、交流の幅を広げられるメリットもあります。
とはいえ、インプットする情報量や頻度が増えると、アウトプットする余裕がなくなってしまいがちです。
活動範囲が広がるほどに、それぞれのコミュニティを使いこなせず中途半端になることも。
だから、個人的には「一つのコミュニティを最大限に活用する」のが効果的な気がします。
コミュニティに参加する価値を高めるには、学んだ知識をアウトプット(行動)する時間も確保すべきです。



もちろん、お金と時間があれば、たくさんのコミュニティに参加したいのが本音ですが…。
まとめ|ライターとして生きていくために
今回は「Webライター向けのコミュニティ」をテーマに、以下のコンテンツを解説しました。
Webライター向けのコミュニティに参加すれば、業務の幅広い知識や切磋琢磨できるライター仲間を得られます。
講師やライター仲間の存在は、新たな挑戦を後押しする原動力でもあります。
僕自身がコミュニティ(Webライターラボ)に参加した理由は、本気でライターとしての人生を続けていくためです。



自分一人では解決しにくい悩みに直面したとき、他者のサポートに頼る大切さを実感しました。
「ライターの業務をずっと続けていきたい」と考えている人は、今回紹介した内容を参考に、コミュニティへの参加を検討してみてください。
当サイトのコンテンツに対する感想を募集しています。
よろしければ、SNSにて「#ライプロ」とタグをつけて自由な感想を発信してみてください!
発信に気づき次第、リプやリアクションなどさせていただきます。
また、以下のようなご意見・ご要望も募集しています。
- わかりにくい部分があった
- 質問してみたいことがある
- こんなコンテンツがほしい
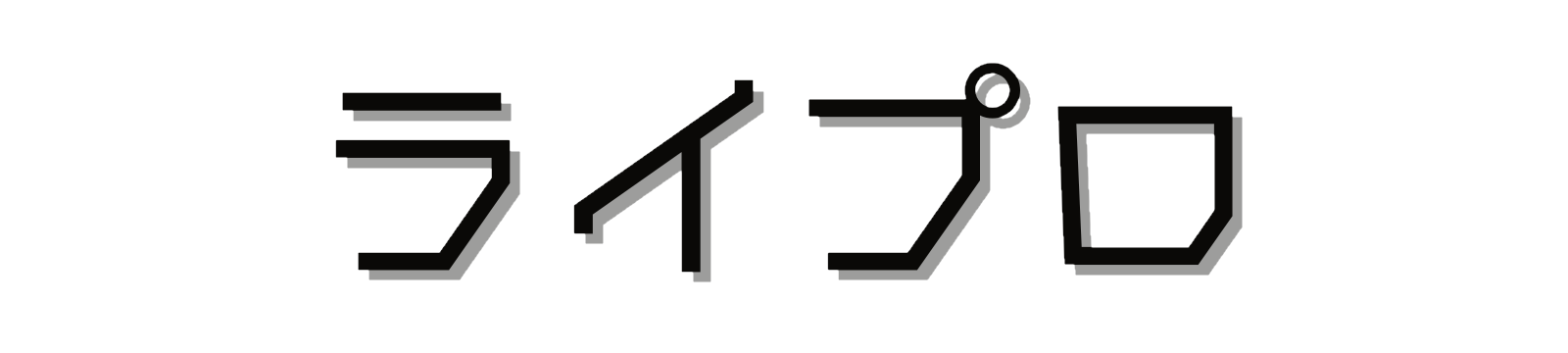
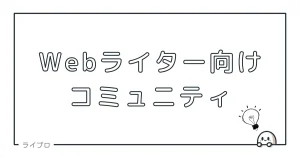
コメント