今回のテーマは「ライターに求められる取材スキル」です。
情報の信頼性が重要視されるWeb記事では、有識者への取材内容をもとに執筆する機会も少なくありません。
僕自身も専門家や監修者を相手に取材対応した経験があります。
取材を成功させるためには、しっかりと「事前準備」をすることが大切です。
運営者プロフィール

- 2020年:未経験からフリーランスのライターに
- 2023年:ライター月収37万円を達成
- 2024年:電子書籍を出版
「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。
運営者プロフィール

- 2020年:未経験でフリーランスのライターに
- 2023年:ライター月収37万円を達成
- 2024年:電子書籍を出版
「文章でどこかの誰かの役に立とう!」をテーマに当サイトを運営しています。SEO・取材・電子書籍など、幅広い案件に対応中。
取材ライターとは
取材ライターは、おもに以下の記事執筆を担当します。
- 取材相手や施設を紹介する記事
- 取材で情報の信頼性を高めたSEO記事
手軽に情報を取得できる現代では、Web記事の信頼性や発信者の権威性が重要視される傾向にあります。
そのため、取材をもとにした記事制作はSEOの主流です。
取材対応をWebライターに依頼するクライアントも増えています。
そこで、まずは以下の観点で取材ライターについて解説します。
取材の重要性
取材が重要視される背景には、Web記事の「E-E-A-T」を求めるトレンドが影響しています。
以下の要素を重要視することから、それぞれの頭文字を取った専門用語。
- Experience(経験)
- Expertise(専門性)
- Authoritativeness(権威性)
- Trustworthiness(信頼性)
専門家や有識者への取材は、Trustworthiness(信頼性)を高める手段として効果的です。
見ず知らずのライターが書いた記事なんて信用できない!
そんな読者の不安を少しでも和らげるためには、権威性がある専門家や有識者の力を借りるべきです。
- 有識者ならではの独自情報を得るため
- 記事内容の信ぴょう性を高めるため
取材ライターの仕事内容
- 取材準備
- 企画・アポ取り
- テーマの調査
- 質問事項の作成
- 取材対応
- 取材記事の執筆
- 記事の監修依頼
(取材相手にチェックを依頼)
取材ライターの仕事は、取材の準備や当日の対応も含まれます。
とくに重要な役割は、取材相手や取材先の企業に対する情報取集です。
基本的に取材相手は初対面のため、知らない分野の専門家を相手にすることも多々あります。
事前知識なしで取材に挑むと、取材相手の話す内容がまったく頭に入ってこないことも。
「たぶん伝わってないんだろうな」は、意外に表情でバレますよ。
おもな取材方法
一般的な取材方法は、以下の3パターンです。
- オンライン
- Zoom
- Microsoft Teams
- Google Meet
- 対面
- 電話
取材の所要時間は、基本的に「30分~1時間」ほどです。
所要時間だけ見ると「長そうだな」と感じるかもしれません。
しかし、実際に取材をしてみると、意外にも時間が不足しがちです。
取材相手がていねいに答えてくれると、後半に急いで質問を消化するケースもありますよ!
また、議事録や録音・録画機能など、取材内容を振り返る手段も用意しておくと便利です。
おもなオンライン会議のツールには録画機能があるので、取材後に振り返りながら執筆できます。
Zoomの無料プランには、時間制限(40分)があるので注意しましょう。
取材ライターに必要なスキル
取材ライターには、習得しておきたい3つのスキルがあります。
情報を整理する|取材前に必要
取材前には、取材テーマの情報を収集・整理するスキルが必要です。
事前に情報を把握しておかないと、取材相手が話す内容を理解できずに進行が滞ってしまいます。
取材の目的は記事に必要な情報を得ることであり、執筆者が専門知識を教わるためではありません。
以下の流れを参考に、事前の情報収集を心がけましょう。
- 取材相手の経歴やWebサイトの情報をリサーチする
- リサーチした情報から質問事項を検討する
- リサーチしてわからないこと:質問する
例)○○について教えてください - リサーチしたらわかること:確認する
例)○○の認識で合ってますか?
- リサーチしてわからないこと:質問する
会話をコントロールする|取材中に必要
取材中は、対面でのコミュニケーションが必要です。
とくに会話をコントロールするスキルが求められます。
- 質問を伝える
- 回答を聞く
- 回答が不十分なら追加で質問する
- 会話が長引いたときは区切りを入れる
取材は時間内に終わらせる必要があり、基本的には「1度きり」です。
取材後に「聞き忘れた」「質問しきれなかった」と悔やんでも、やり直しのチャンスは期待できません。
だからこそ、限られた時間で取材相手の情報を引き出すコミュニケーションが必要です。
質問ごとに時間を割り振って予行練習するのも効果的!
文字起こしする|取材後に必要
取材後には、取材中の会話内容を文字起こしするスキルが必要です。
取材の文字起こしは、動画や音声ファイルを見直す必要があります。
そのため、文字起こしには取材時間×1.5倍の所要時間を想定すべきです。
文字起こしする手間を省くためには、取材中に少しでも内容を理解できるような工夫・準備が欠かせません。
また、ただ文字起こしするだけではなく、記事に掲載できる文章に編集する必要もあります。
テキストデータだけでも効率的に作成したい場合は、AI文字起こしサービス
ただし、無料の文字起こしツールは、再生時間やファイルサイズに制限があるので注意しましょう。
取材の失敗を防ぐコツ
取材を失敗しないためには、事前準備がとにかく重要です。
取材相手は基本的に初対面であり、知らない分野の専門家を相手にすることも多々あります。



僕自身も過去に「美容家」「英会話教師」などの不慣れなジャンルで取材した経験があります。
そこで、実際の取材で得た経験や工夫をもとに、取材の失敗を防ぐ「6つのコツ」を紹介します。
取材の目的を把握する
まずは、取材の目的を把握しましょう。
取材の目的により、質問すべき内容が異なるからです。
- 記事の信ぴょう性を高めたい
→情報の正誤を確認する - 記事の独自性を高めたい
→取材相手の体験談を聞き出す - 取材相手や施設を紹介したい
→相手の歴史や考え方を深堀りする
記事に書かないような内容を質問しても、せっかく取材した情報と時間を無駄にしてしまいます。
また、取材相手との認識がズレないように、質問事項を事前に伝えておきましょう。
見出し構成を事前確認する
取材で質問する内容は、基本的に「見出し構成」から検討します。
つまり、取材で確認すべき内容は「記事に書くべき情報」です。
質問事項を見出し構成から考えると、確認すべき内容の漏れを防げます。
ライター自身が見出し構成を作成しない場合は、事前にクライアントから提供してもらいましょう。
質問事項を取材相手と事前共有する
取材の目的や質問事項は、前日までに取材相手と情報共有をしておきましょう。
取材相手が、取材に慣れているとは限りません。
インタビュアー側と同様に、取材相手にも準備が必要です。
たとえ専門知識に長けていても、その場で質問された内容にはスムーズに回答できないことも考えられます。
取材相手も事前準備できるように工夫するのが、回答の充実度を上げるための重要なポイントです。
相手に負担をかけないためには、フリートークをさせない意識も大切!
質問事項に「想定する回答」を記載する
事前共有する質問事項には、できる範囲で想定する回答も記載してみましょう。
また、回答が「はい」「いいえ」のひと言で完結するように、質問を考慮しておくのが理想的です。
取材は想定より時間がかかるため、質問数が多いと取材相手に負担をかける可能性もあります。
想定した回答が取材相手の認識と一致していれば「そのとおりです」のひと言で解決です。
質問数が多いときの「時短テク」としても効果的です。
取材のテーマを事前にリサーチする
取材テーマに関連する知識は、事前にリサーチしておきましょう。
取材相手が話す専門的な知識や用語を理解できないと、取材中に思考がついていきません。
また「たぶん理解してなさそうだな」という雰囲気は、意外にも表情から相手に伝わってしまいます。
取材中は話が脱線することも多々あるため、内容をまとめながら進めるのが理想的です。
取材相手が一方的にしゃべると「何の話でしたっけ?」ってなりがち。
取材中に信頼関係を築く
取材中に取材相手との信頼関係を築くことも重要なポイントです。
取材相手との会話が弾むと、想定外な「とっておき」のエピソードを引き出せることもあります。
「実はこの前、こんなことがあって~」のような内容が意外に重要。
信頼関係を築くためのポイントは、以下のとおりです。
- 相手の負担を減らすこと
- 無知な状態で対応しないこと
- 会話が一方通行とならないこと
専門知識のない素人が考えた質問は、あくまでも「基本的な内容」が中心です。
当初想定していなかったエピソードほど、記事の独自性を高めるためには重要だったりもします。
用意した質問はさっさと済ませて、余った時間で「伝えきれていない情報(想い)ってありますか?」と聞いてみましょう!
取材トラブルを回避する対策
取材対応では、思わぬトラブルが発生することもあります。
とくに取材後の記事執筆で「取材相手との認識のズレ」が生じるケースに注意が必要です。
今回は、よくある3パターンのトラブルを紹介します。
取材相手の意思に反する内容を書かないこと
取材記事では、取材相手の言葉や考えをストレートに伝えるべきです。
執筆者のニュアンスで言葉を変えてしまうと、取材相手との認識のズレが生じてしまいます。
また、執筆者の自己判断を、あたかも取材相手の言葉のように伝えるのも厳禁です。
取材相手から「こんなこと言った覚えがない」とクレームが入ってしまいます。
取材相手との信頼関係を築くためにも、執筆記事の監修(チェック)も含めて依頼しておきましょう。
他者(他社)の評価を下げないこと
取材相手が提供する商品やサービスを紹介する場合は、他者(他社)の評価を下げないように注意しましょう。
取材相手を露骨に評価してしまうと、相対的に他者(他社)の評価が下がるような印象を与えてしまいます。
露骨な印象操作は、取材相手の印象が悪化してしまう要因にもなりかねません。
取材の目的は、あくまでも取材相手から得た情報を伝えることです。
商品やサービスの比較記事を執筆する場合は、取材相手のためにも公平性を保つ意識を心がけましょう。
連絡のやり取りが滞らないこと
取材相手との連絡は、滞らないように注意しましょう。
取材相手を「待たせる」「放置する」ことは、担当者だけでなくクライアントの評価を下げる要因にもなります。
とある担当者が取材依頼の返信に気づかず放置していた。
依頼を受けた相手は、放置されたことに憤りを感じ、SNSへ不満を投稿。
結果として、担当者が所属するクライアントの評価を下げてしまうことに。
取材記事は、取材相手との信頼関係があって成立します。
社会人のマナーとして、スムーズな連絡のやり取りを心がけましょう。
まとめ|事前準備がとにかく重要!
今回は「ライターに求められる取材スキル」をテーマに、以下のコンテンツを解説しました。
Contents
取材ライターが取材を成功させるコツは、しっかりと事前準備をすることです。
僕自身もディレクターとして、ライターさんに取材対応を依頼した経験があります。
しかし、9割くらいは断られました。
だからこそ、取材対応できるライターは、クライアントから重宝される貴重な存在です。
取材をとおして話を伺うと、有識者ならではの興味深い知識や考え方を学べます。
ネットの情報だけを調べるよりも内容が濃く、より充実した記事を執筆できます。
慣れていない業務には不安を感じてしまいますが、できることが増えると楽しさが倍増しますよ!
当サイトのコンテンツに対する感想を募集しています。
よろしければ、SNSにて「#ライプロ」とタグをつけて自由な感想を発信してみてください!
発信に気づき次第、リプやリアクションなどさせていただきます。
また、以下のようなご意見・ご要望も募集しています。
- わかりにくい部分があった
- 質問してみたいことがある
- こんなコンテンツがほしい
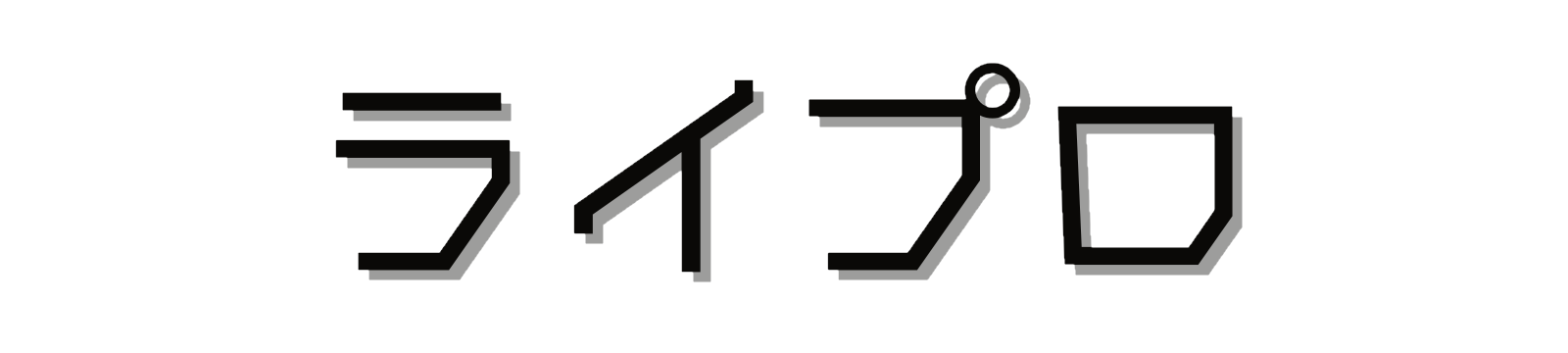
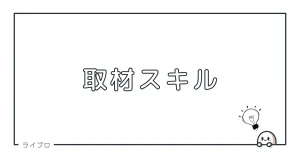
コメント